買い上げ点数を上げる方法やポイントについて解説

ドラッグストアやスーパーマーケットといった小売業界において、「買い上げ点数」の向上は、客単価・売上アップに直結する重要な課題です。
近年、競争の激化や消費者の購買行動の多様化により、「ついで買い」を促すための施策は、これまで以上に重要性を増しています。
効果的な陳列方法や接客、さらにはデジタル技術を活用したアプローチなど、多角的な戦略が求められているのが現状です。
そこで、この記事では、大手ドラッグストアやスーパーマーケットの店舗運営部の方々に向けて、「買い上げ点数」を向上させるための具体的な方法や、店舗で実践できる具体的なポイントを徹底的にご紹介いたします。
エイジスのマーチャンダイジングサービス
商品の補充や品出し、棚替え、改装など、様々な頻度で発生する店舗の”売場づくり”をすべてサポートします。
本資料では、サービスの概要や実績などをまとめて紹介しております。ぜひご覧ください。
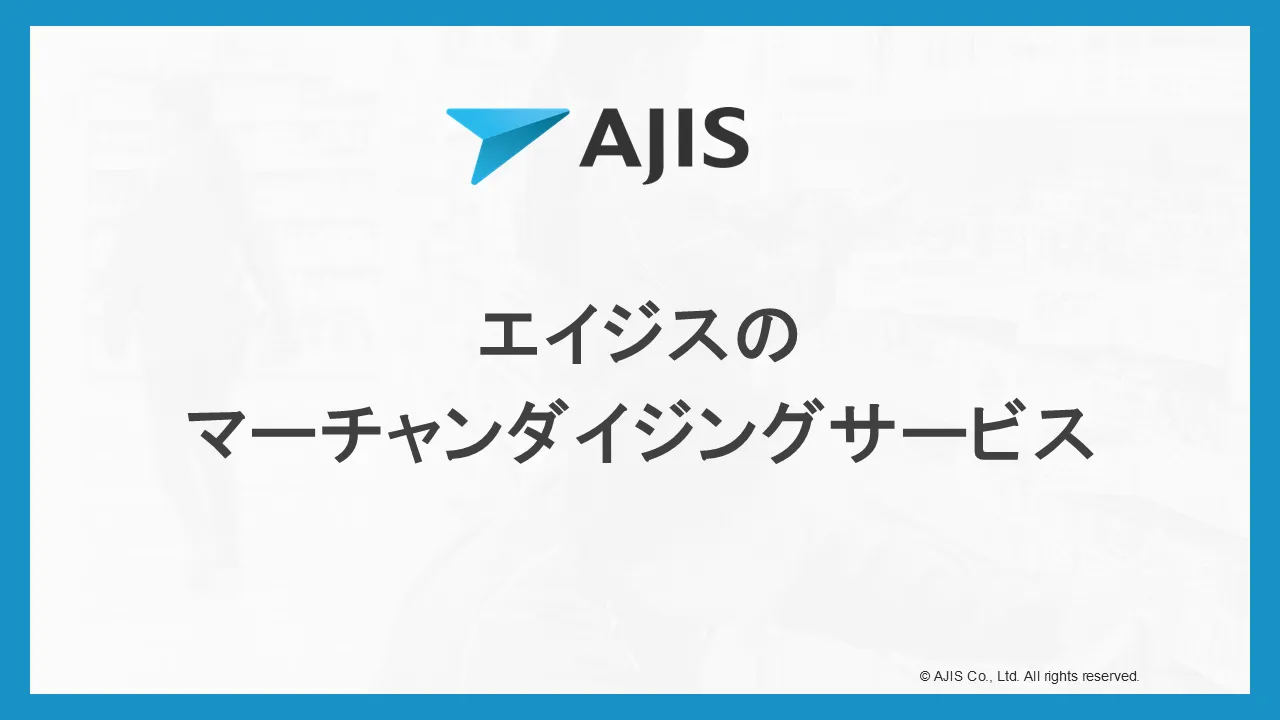
売上の仕組み
買い上げ点数を向上させる意義について知るには、まず売上の仕組みを考えることが近道です。
買い上げ点数の定義と客単価・売上の関係性
ドラッグストアやスーパーマーケットといった小売業界における買い上げ点数とは、顧客が1回の買い物で購入した商品の合計点数を示す重要な指標です。
店舗の売上高は、客数、客単価という2つの大きな要素から構成されています。
売上高=客数×客単価
そして、客単価はさらに以下の要素に分解できます。
客単価=買い上げ点数×商品単価
この計算式から、売上を向上させるためには、客数を増やすか、客単価を上げるかのいずれか、あるいは両方を達成する必要があることがわかります。
特に、買い上げ点数の向上は、来店している顧客に対して「ついで買い」を促すことによって客単価を直接的に引き上げる効果があるため、店舗運営部にとって非常に効率的な施策となるのです。
売上を向上させるには、非計画購買の促進が重要
新規顧客の獲得コストが増加傾向にある現在、来店している顧客一人当たりの購買額を増やすことは、企業の収益性を高める上で非常に重要です。
買い上げ点数を増やすということは、顧客の「非計画購買(衝動買い)」をいかに促せるかにかかっています。
非計画購買とは、来店前には買う予定のなかった商品を結果的に購入することです。
店舗運営においては、この「ついで買い」を誘発する仕掛けを売場全体に戦略的に組み込むことが、売上増加に直結する持続的な成長の鍵となります。
買い上げ点数を上げる方法
買い上げ点数を高めるための施策は、主に陳列や動線の工夫によって、顧客の購買意欲を喚起し、購買行動をサポートすることに集約できます。
以下で、具体的な方法をご紹介します。
ゴールデンゾーン
ゴールデンゾーンとは、顧客が最も見やすく、手に取りやすい高さや範囲を指す陳列棚のエリアです。
一般的に、160~170cmの成人が自然な姿勢で目にする高さ(床から約75~135cm)がゴールデンゾーンに該当するといわれています。
この高さは店舗の主な客層(成人か子供か、男女比など)の平均身長によっても変動します。
ゴールデンゾーンは、販売促進に最適な場所であるため、新商品や売れ筋商品、高付加価値商品など、店舗が特に売りたい商品を陳列することで、顧客の視界に入りやすくなり、買い上げ点数の向上に貢献します。
顧客は棚全体をくまなく見るのではなく、主に目の高さから腰の高さの範囲を見る傾向にあるため、このゾーンの戦略的な活用が欠かせません。
ゴールデンゾーンについて詳しくは、下記の記事をご覧ください。
【関連記事】
ゴールデンゾーン活用術!基本と売上を伸ばす陳列テクニックを紹介
動線の工夫
店舗の動線設計は、顧客が店内をどのように移動するか、すなわち回遊性に直結します。
顧客の動線が適切に設計されていないと、通路が狭く感じたり、目的の商品だけを購入してすぐに退店したりするなど、購買機会の損失につながります。
買い上げ点数を増やすためには、顧客の店舗滞在時間を伸ばし、より多くの商品と接触する機会を増やす動線を設計することが重要です。
具体的な工夫としては、以下のようなものがあります。
- 人気商品や集客力のある商品を店舗の奥に配置し、そこへ誘導する過程で他の商品を見てもらう流れを作る。
- 通路の折れ角や入口付近など、顧客が立ち止まりやすい場所に、目を引く季節商品や特売品を陳列する。
顧客がスムーズに、かつ自然に店内を回遊できる動線は、買い物のストレスを減らし、満足度を高めることにもつながります。
買い上げ点数を上げるためのポイント
店舗運営部が現場で実践し、効果測定を行いやすい具体的な施策をご紹介します。
売れている商品の組み合わせを知る
勘や経験ではなく、POSデータや購買履歴を活用したデータ分析が、買い上げ点数アップの確実性を高めます。
特に有効なのがバスケット分析です。
バスケット分析とは、顧客が一度に購入する商品の組み合わせ(バスケットの中身)を調べる手法です。
これにより、「A商品を購入する顧客は、高い確率でB商品も一緒に購入している」といった、併せ買いされやすい商品の相関を洗い出すことができます。
この分析結果をもとに、実際に商品の陳列をセットで行うなど、関連性の高い商品の組み合わせを売場に反映させることで、クロスマーチャンダイジングの精度を格段に向上させることが可能です。
関連商品を近くに配置する
バスケット分析などで得られた「売れる組み合わせ」の情報をもとに、関連性の高い商品を意図的に近くに陳列するクロスセリング(クロスマーチャンダイジング)を実行しましょう。
顧客には、商品を探す手間をかけたくないという心理があります。
そのため、「牛肉」の近くに「焼肉のタレ」を置くなど、使用シーンが共通する商品や、一方の商品の使用に欠かせない商品を近接して配置することで、「ついで買い」を誘発しましょう。
ドラッグストアであれば、熱中症対策コーナーに「経口補水液」や「日焼け止め」を置くなどの具体例が挙げられます。
クロスマーチャンダイジングについて詳しくは、下記の記事をご覧ください。
【関連記事】
クロスマーチャンダイジングとは?小売業の売上を伸ばす戦略を紹介!
商品の陳列を定期的に変えてみる
顧客は、慣れた店舗ではいつも決まったルートで目的の商品だけを購入しがちです。
陳列場所やレイアウトを定期的に変更しなければ、顧客は店舗に飽きを感じてしまい、新しい商品やその他の商品に目を留める機会が減少してしまうでしょう。
陳列を定期的に変更することで、顧客に新たな気持ちで店内を回遊してもらい、今まで気づかなかった商品を発見してもらうきっかけを生み出すことが、買い上げ点数の増加につながります。
陳列について詳しくは、下記の記事をご覧ください。
【関連記事】
商品が売れるディスプレイの仕方とは?商品陳列の基本やテクニックも解説!
陳列量や方法を工夫する
陳列の「量」や「見せ方」も購買意欲に大きく影響します。
次のような工夫が効果的です。
- 量感陳列…新商品や特売品などを大量に積み上げ、視覚的なインパクトとお買い得感を強調します。
- 前進立体陳列…棚の手前(顧客から見える面)に商品を高く配置し、棚全体に商品が豊富に揃っている印象を与える陳列方法で、品揃えの豊富さや在庫切れしない安心感を顧客にアピールできます。
- ジャンブル(なげこみ)陳列…ワゴンや平台などの什器に、商品をあえて無造作に積み上げたり、投げ込んだりして陳列する方法で、「お買い得感」や「宝探し感」を与え、購買意欲を刺激する効果があります。
- エンド陳列…通路の突き当たりなど目立つ場所に、力を入れている商品を陳列することで、顧客の足を止めさせます。
- 顧客目線の配慮…シャンプーや洗剤といった重いかさばる商品は、カートに入れやすいよう下段に陳列するなど、顧客の利便性を考慮した配置も、ストレスなく購買を促すために重要です。
買い上げ点数を上げる売場づくりにおすすめのサービス
エイジスグループでは、買い上げ点数を上げるための売場づくりに貢献する、さまざまなマーチャンダイジングサービスメニューをご用意しております。
- 集中補充(商品補充・品出し)…店舗スタッフに代わり品出しを行います
- 季節の棚替え・カテゴリーリセット…エイジスグループが定期的な棚替えを担当します
- 新店準備・改装リモデル・閉店作業…改装等に伴う什器解体・設置
- 売場の欠品・売価チェック…欠品商品のデータをレポート
- 賞味期限チェック…フードロス対策(食品ロス対策)に IT と人的リソースを組み合わせた次世代型賞味期限チェックサービスをオススメします
エイジスグループのマーチャンダイジングサービスについて詳しくは、下記の詳細ページをご覧ください。
https://service.ajis.jp/service/merchandising.html
まとめ
買い上げ点数の向上は、「客数×客単価」で決まる売上構造において、客単価を効率よく引き上げるための最重要戦略の一つです。
成功の鍵は、顧客の「非計画購買(ついで買い)」を意図的に引き起こす、戦略的な売場づくりにあります。
具体的には、ゴールデンゾーンを最大限に活用し、動線を工夫して顧客の回遊性と滞在時間を延ばすことが基本です。
さらに、バスケット分析によって「売れている組み合わせ」を正確に把握し、関連商品の近接陳列を徹底することで、施策の確度が高まります。
陳列の定期的な変更や、AIを活用した棚割最適化などのデジタル技術も組み合わせることで、経験や勘に頼らない、持続的な店舗成長を実現できるでしょう。
これらの手法を組織的に実践し、買い上げ点数アップに結びつけることが、今日の厳しい小売競争を勝ち抜くための重要な一歩となります。



