ゴールデンゾーン活用術!基本と売上を伸ばす陳列テクニックを紹介

ドラッグストアやスーパーマーケット、ホームセンターといった小売業の店舗運営において、いかにして商品の売上を最大化するかは常に重要な課題です。
特に、新規顧客の獲得が難しいとされる現代では、既存の来店客にいかに多くの商品を手に取ってもらい、購入につなげるかが鍵となります。
そのために欠かせないのが、消費者の購買心理に基づいた「陳列」の工夫です。 なかでも、売上を大きく左右すると言われるのが「ゴールデンゾーン」の活用です。
ゴールデンゾーンとは、顧客が最も商品を認識しやすく、手に取りやすい棚の高さや範囲を指します。ゴールデンゾーンを戦略的に活用することで、来店客の購買意欲を向上させ、売上アップを図ることが可能になります。
しかし、ゴールデンゾーンの定義は、顧客層や店舗の状況によって常に変化します。そのため、「これで完璧」という画一的な陳列方法だけでは、最大の効果は得られません。
そこで、この記事では、店舗運営に携わる担当者の皆様に向けて、ゴールデンゾーンの基本的な知識から、客層や店舗環境に合わせた具体的な陳列テクニックまで、売上を伸ばすための実践的な活用術をご紹介いたします。
商品の補充や品出し、棚替え、改装など、様々な頻度で発生する店舗の”売場づくり”をすべてサポートします。 本資料では、サービスの概要や実績などをまとめて紹介しております。ぜひご覧ください。エイジスのマーチャンダイジングサービス
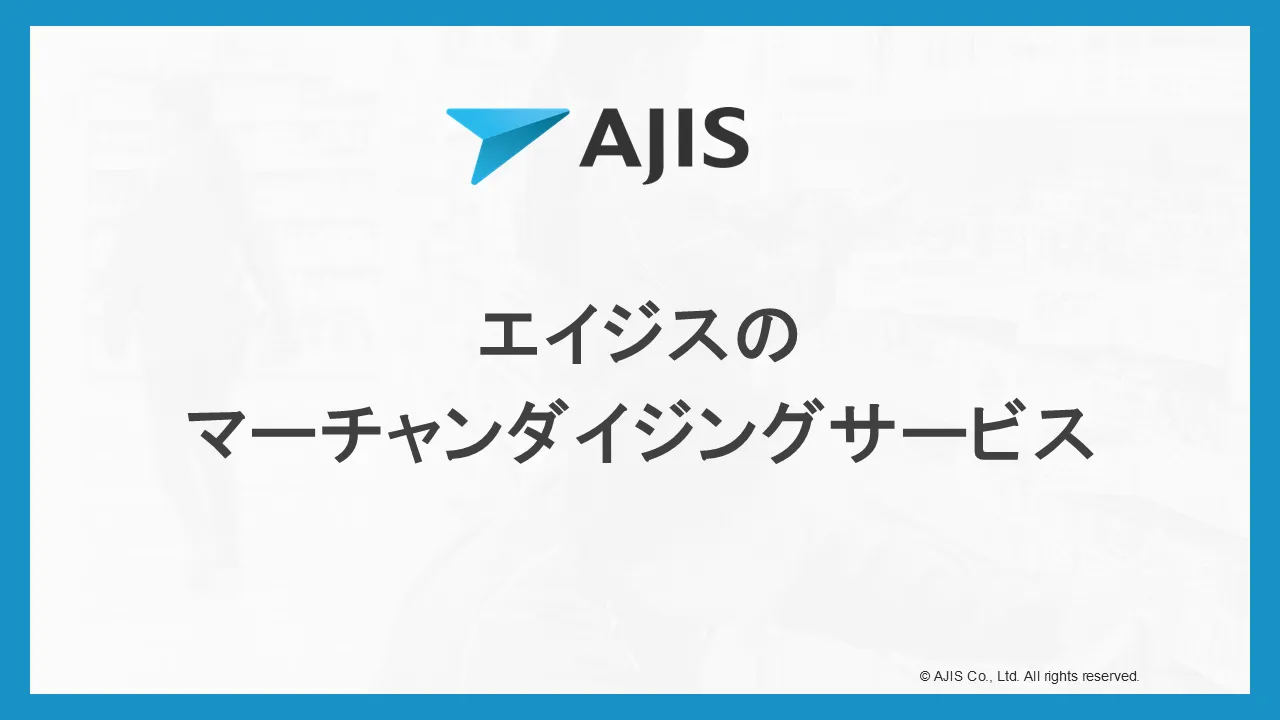
ゴールデンゾーンとは?
店舗の売上を伸ばすための陳列方法を考える上で、まず理解しておきたいのが「ゴールデンゾーン」です。
ゴールデンゾーンとは、来店客の視線に入りやすく、また手に取りやすい高さにある棚の範囲を指します。 一般的に、身長160~170cmの成人が自然な姿勢で目にする高さ(床から約75~135cm)がゴールデンゾーンに該当するといわれています。
商品の視認性は、売上に直接的な影響を与えます。なぜなら、顧客の視界に入らない商品は、そもそも購入の選択肢にすら上がらないからです。そのため、店舗運営においては、ゴールデンゾーンをいかに戦略的に活用し、顧客の目に留まる商品を配置するかが、売上向上における重要なポイントとなります。
ゴールデンゾーンとゴールデンラインの違い
ゴールデンゾーンと似た言葉に「ゴールデンライン」があります。 ゴールデンゾーンが床からの高さの範囲を指すのに対し、ゴールデンラインは「視線」を指します。
たとえば、一般的に、来店客の視線は入り口から左斜め前へと流れるといわれています。 また、棚などを見る際は、左上から右下へ見ることが多いです。 このように、視線を考えて商品を陳列することで来店客の目に入りやすくするのが、ゴールデンラインの活用です。
ゴールデンゾーンに配置するべき商品
ゴールデンゾーンは、来店客が最も商品を手に取りやすい位置にあるため、店舗の主力商品や新商品、特売品といった「売りたい商品」を配置することが推奨されます。 ゴールデンゾーンにこれらの商品を配置することで、来店客の目に留まりやすく、購入につながりやすくなります。
特に、チラシに掲載されているような集客力のある商品をゴールデンゾーンに置くことで、来店客の購買意欲を高める効果が期待できます。 また、季節限定の商品や、競合店との差別化を図りたい商品を配置するのも有効な戦略です。
ゴールデンゾーンの重要性と効果
ゴールデンゾーンがなぜ重要なのか、もう少し深く掘り下げていきましょう。
商品の視認率の向上
ゴールデンゾーンを活用することで、商品の視認率を向上させることができます。 来店客は、商品を探す際、無意識のうちに自分の目線の高さや手の届く範囲にある商品を優先的に見ています。
ゴールデンゾーンに商品を配置することで、こうした来店客の行動パターンに合致した陳列が可能となり、商品が目に留まる機会が増加します。
また、ゴールデンゾーンにある商品は、来店客が自然な姿勢でじっくりと商品パッケージや商品説明を見ることができるため、それ以外の棚にある商品よりも比較検討がしやすくなります。
このため、種類が多いカテゴリの商品を陳列するのも良いでしょう。
購買意欲の向上
ゴールデンゾーンに商品が置かれていることで、来店客から単に見つけてもらいやすくなるだけでなく、購買意欲の向上も見込めます。
商品が手に取りやすい位置にあるということは、来店客にとってストレスなく商品を選べるということです。 つまり、手に取りにくいほかの商品をわざわざ手に取って比較する手間が省かれ、購買につながりやすくなるのです。
知っておくべきゴールデンゾーンの位置と高さ
さらに、ゴールデンゾーンの具体的な位置や高さについても見ていきましょう。
ターゲットで異なるゴールデンゾーンの位置と高さ
ゴールデンゾーンの高さは、ターゲットとなる顧客層によっても異なります。
「ゴールデンゾーンとは?」では、「一般的に、身長160~170cmの成人が自然な姿勢で目にする高さ(床から約75~135cm)がゴールデンゾーンに該当する」とお伝えしましたが、たとえば、成人男性と女性では平均身長が異なるため、それぞれに合わせたゴールデンゾーンの高さを設定する必要があります。
女性向けの商品であれば、女性の平均身長(155cm前後)に合わせた高さに設定すると効果的です。
また、子供向けのおもちゃやお菓子などを陳列する場合は、子供の目線に合わせた、より低い位置がゴールデンゾーンとなります。 子供と一口に言っても、幼児と中学生では身長が大きく異なるため、細かいターゲット層に合わせた設定が求められます。
このように、誰に買って欲しいかを明確にして、陳列する位置を調整することが大切です。
通路の幅で異なるゴールデンゾーンの位置と高さ
店舗の通路の幅も、ゴールデンゾーンに影響を与えます。 通路が広い店舗では、顧客が商品から少し離れた位置から全体を俯瞰して商品を選ぶため、ゴールデンゾーンが比較的、広くなります。
一方、通路が狭い店舗では、顧客は商品に近づいて見る傾向にあるため、ゴールデンゾーンは狭く、上段に限定される傾向にあります。
このため、通路の幅に合わせてゴールデンゾーンを意識した陳列方法を調整することが重要です。
什器の種類で異なるゴールデンゾーンの位置と高さ
什器の種類によってもゴールデンゾーンの位置と高さは変わってきます。
たとえば、垂直型ゴンドラのゴールデンゾーンが床から約75~150cmであるのに対し、張り出し型ゴンドラの場合、最も来店客の目を引くのは張り出し部で、通常は最下段付近となっています。
また、冷蔵・冷凍ケースの場合は、床から80cm~135cm程度の高さがゴールデンゾーンに該当します。
このように、一般的なゴールデンゾーンとは異なる什器も多いため、一律に高さを決めるのではなく、什器の特性に応じたゴールデンゾーンを理解して陳列を行う必要があります。
ゴールデンゾーンの活用テクニック
最後に、ゴールデンゾーンの活用テクニックを4つご紹介します。
売筋商品・売りたい商品を配置する
ゴールデンゾーンに配置する商品は、その店舗の売上を大きく左右します。
特に、季節の売れ筋商品や新商品、期間限定の商品、あるいは利益率の高い商品を優先的に配置することで、店舗全体の売上向上につなげることができます。
また、チラシに掲載された商品をゴールデンゾーンに置くことで、広告の効果を最大化できるでしょう。
ターゲットに合わせた位置と高さに配置する
「ターゲットで異なるゴールデンゾーンの位置と高さ」でもご紹介したように、ゴールデンゾーンを最大限に活用するには、誰に商品を届けたいかを明確にし、ターゲット層の身長に合った位置と高さに商品を配置することが重要です。
たとえば、男性向けの商品であれば、男性の平均的な身長(170cm前後)を考慮して陳列の高さを調整する必要がありますし、高齢者向けの商品であれば、杖をついたり車椅子に乗った方の目線に合わせて低い位置に配置することで、商品が手に取られやすくなります。
視線の動きを意識して商品を配置する
「 ゴールデンゾーンとゴールデンラインの違い」でもご紹介したように、ゴールデンゾーンだけでなく、視線を意識して陳列することも大切です。
入り口から左前までのラインや、棚の左上から右下へのライン、左上から右、さらに左下から右へと「Z」を描くラインなど、一般的な人の視線の動きも意識して配置しましょう。
商品特性に合わせた陳列方法を活用する
商品の特性に応じて、陳列方法を工夫することも重要です。
たとえば、高価格品やブランド品など、高級感を演出したい商品は、ゴールデンゾーンよりも高めの位置に陳列した方が効果的です。
逆に、セール品や見切り品は、ゴールデンゾーンの中でも低めの高さでカゴや平台のジャンブル陳列を行うことで、「お手軽感」「掘り出し物」イメージを訴求できます。
また、関連商品同士を隣接して陳列する「クロスマーチャンダイジング」は、顧客が複数の商品を一度に購入する機会を増やし、客単価の向上に貢献します。
陳列については、下記の記事もご覧ください。
【関連記事】
「クロスマーチャンダイジングとは?小売業の売上を伸ばす戦略を紹介!」
まとめ
ゴールデンゾーンとは、顧客が最も商品を認識しやすく、手に取りやすい棚の高さを指し、一般的には床から75cmから135cmの範囲とされています。
ゴールデンゾーンを効果的に活用するためには、ターゲット顧客の特性や店舗の環境、そして通路の幅を考慮した上で、売れ筋商品や主力商品を配置する戦略が不可欠です。
エイジスグループでは、次のようなサービスでお客様のゴールデンゾーンを活用した売場作りをサポートしています。
集中補充(商品補充・品出し)
店舗スタッフに代わって商品の補充や品出しを行います。
開店前やピークタイムに作業を完了させることで、売り場の状態を最適に保ちます。
これにより、店舗スタッフは接客や販売といったコア業務に集中でき、売上アップにつなげることが可能です。
エイジスの「集中補充(商品補充・品出し)」サービスについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
https://service.ajis.jp/service/merchandising/display-replenishment.html
季節の棚替え・カテゴリーリセット
当社の専門チームが、店舗スタッフに代わって棚替えを迅速に実行します。
営業中に作業が可能なため、販売機会を失う心配もありません。52週MD計画に基づいた棚替えも、短期集中で正確に完了させます。
エイジスの「季節の棚替え・カテゴリーリセット」サービスについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
https://service.ajis.jp/service/merchandising/display.html
新店準備・改装リモデル・閉店作業
新店オープンや改装、閉店に関わるあらゆる業務をエイジスグループが一括して承ります。
事前の打ち合わせから、什器の設置、商品陳列に至るまで、全てを専門チームが代行します。営業中や深夜の作業も可能なため、店舗を休業する必要がありません。
これにより、販売機会を失うことなく、顧客の離反を防ぎます。
エイジスの「新店準備・改装リモデル・閉店作業」サービスについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
https://service.ajis.jp/service/merchandising/display-remodelling.html



