クロスマーチャンダイジングとは?小売業の売上を伸ばす戦略を紹介!

「あの商品とこの商品を一緒に買うお客さんが多いな…」
「季節の変わり目で売上が伸び悩んでいる…」
日々、店舗の運営に携わる中で、そんな風に感じることはありませんか?
顧客の購買行動は複雑で、単に商品を並べるだけでは売上アップにつながりません。
そこで注目すべきなのが、「クロスマーチャンダイジング」という売場戦略です。
本コラムでは、ドラッグストアやスーパーマーケットをはじめ、店舗運営を担う皆様に、クロスマーチャンダイジングの基本やメリット・デメリットをご理解いただけるよう、解説いたします。
エイジスのマーチャンダイジングサービス
商品の補充や品出し、棚替え、改装など、様々な頻度で発生する店舗の”売場づくり”をすべてサポートします。
本資料では、サービスの概要や実績などをまとめて紹介しております。ぜひご覧ください。
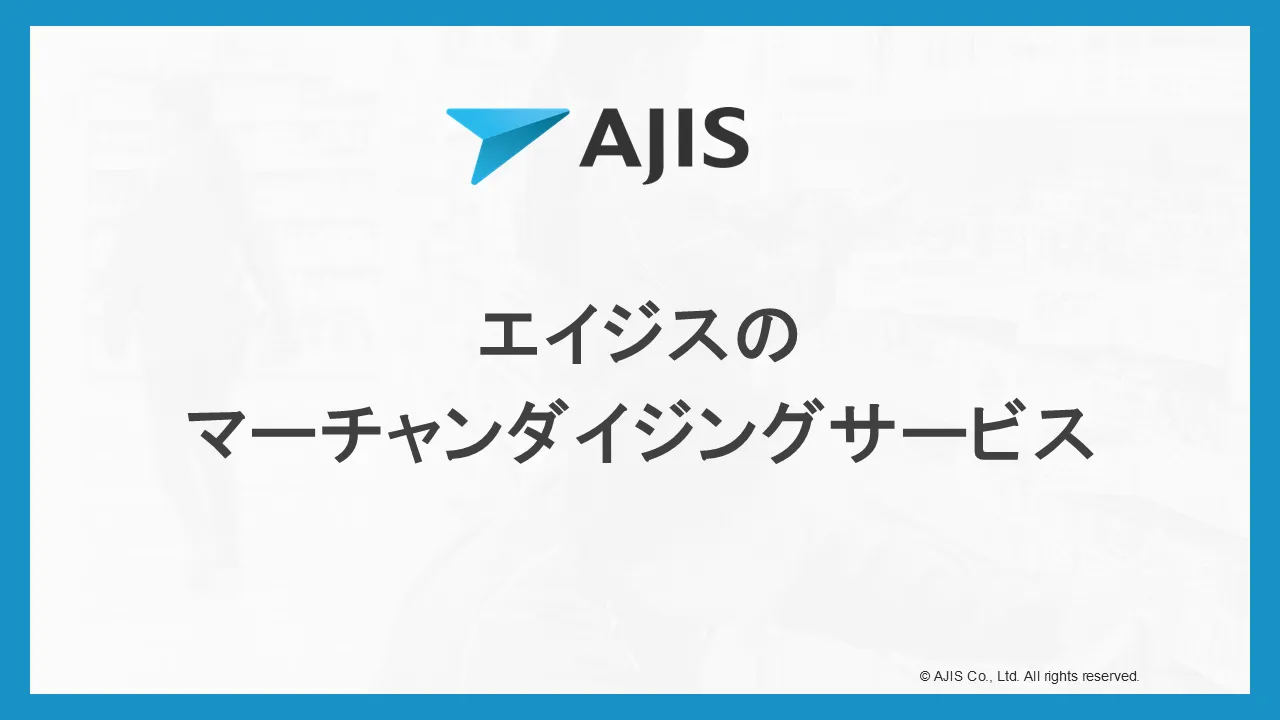
クロスマーチャンダイジング(クロスMD)とは?
クロスマーチャンダイジング(Cross Merchandising)とは、関連性の高い商品を組み合わせて陳列する売場づくりの手法のことです。
たとえば、スーパーマーケットで牛肉売場の隣に焼肉のタレを置いたり、ドラッグストアで風邪薬の隣にのど飴や栄養ドリンクを置いたりする陳列方法がこれにあたります。
お客様の購買行動には、「Aという商品を買う人はBという商品も買う傾向にある」というように、傾向があります。
この関連性を活用し、お客様が次に買いたい商品を予測して、買い忘れのない快適な買い物体験を提供しつつ顧客単価アップを狙うのが、クロスマーチャンダイジングの目的です。
クロスマーチャンダイジングのメリット
クロスマーチャンダイジングは、店舗と顧客の双方に多くのメリットをもたらします。
店舗側のメリット
まずは、店舗側のメリットをご紹介します。
客単価と売上が向上する
クロスマーチャンダイジングの最大のメリットは、客単価と売上の向上です。
関連商品を一緒に陳列することで、お客様に商品をまとめて購入してもらいやすくなります。
その結果、1人あたりの購買金額が増加し、店舗全体の売上アップにつながります。
顧客満足度とロイヤリティが向上する
お客様にとっては、商品を探す手間が省け、買い忘れも防げるため、買い物体験がよりスムーズになります。
こうした「気が利く」陳列が、お客様の満足度や、店舗へのロイヤリティ(忠誠心)を高めます。
良い買い物体験はリピート来店を促し、長期的な売上基盤の強化にもつながるでしょう。
在庫回転率と機会損失の改善につながる
関連性の高い商品をまとめて陳列することで、通常では単体であまり売れない商品や、季節性が高い商品なども連動して売れやすくなります。
この結果、個々の商品の在庫が効率的に動くようになり、店舗全体の在庫回転率が向上します。売れ残りを減らし、保管コストを抑える効果も期待できます。
また、機会損失の改善にもつながります。
機会損失とは、お客様が買いたい商品があったにもかかわらず、品切れなど売場での品切れ、または商品を見つけることができず、購入できなかったために失われた販売機会のことです。
たとえば、鼻炎薬は薬品コーナーに、マスクは衛生用品コーナーに、保湿ティッシュは日用品コーナーに陳列されていた場合、お客様は鼻炎薬だけを買って帰ってしまうかもしれません。
クロスマーチャンダイジングによって一ヵ所にまとめて陳列することで、鼻炎薬とマスク、保湿ティッシュをすべて購入してもらえ、機会損失を防止できる可能性があります。
顧客側のメリット
店舗側だけでなく、顧客側にもメリットがあります。
買い物の時間を短くできる
お客様は、関連商品が同じ場所にまとまっていることで、店内をあちこち探しまわる必要がなくなります。
目的の商品と、それに付随する商品が効率よく見つかるため、買い物の時間を大幅に短縮できます。
新しい発見やメニューのアイデアを得られる
関連商品が近くに陳列されていることで、お客様は「そういえばこれも必要だった」と思い出したり、新しい使い方や組み合わせに気づいたりします。
たとえば、スーパーマーケットであれば、メイン商品から連想されるメニューのヒントを得ることもでき、より豊かな買い物体験につながります。
より良い商品選択ができる
クロスマーチャンダイジングでは、シャンプーの近くにコンディショナーやトリートメントを置くというように、関連商品が同じ場所にまとめて陳列されるため、顧客にとって比較検討がしやすくなり、より良い商品選択ができる可能性が高まります。
また、顧客は自分一人では気づかなかったかもしれない新たな選択肢を発見できるため、より賢く、より満足度の高い商品選択ができるようになります。たとえば、喉が痛くて風邪薬を買いに来た顧客が、隣に陳列されたトローチ薬やのど飴を見て、「まだ症状が軽いからのど飴で様子を見よう」と考える、といったケースが挙げられます。
クロスマーチャンダイジングのデメリット
一方、クロスマーチャンダイジングにも、デメリットはあります。
店舗側と顧客側、それぞれの視点からご紹介します。
店舗側のデメリット
まずは、店舗側に発生する可能性もあるデメリットを確認していきましょう。
陳列や在庫管理が複雑になる
通常のカテゴリー陳列と異なり、複数のカテゴリーの商品をまとめて陳列するため、陳列や在庫管理が複雑になります。
特に、複数の場所に同じ商品を多箇所陳列する場合、バックヤードの在庫管理が煩雑になる可能性があります。
非効率な売場スペースになる可能性がある
クロスマーチャンダイジングの企画が不適切だと、売場全体の効率を損なう可能性があります。
顧客のニーズを十分に分析せずに商品を組み合わせると、本来は売れるはずだった商品の陳列スペースが奪われ、機会損失が発生します。
ブランドイメージがぼやけてしまう
陳列する商品の組み合わせによっては、ブランドイメージがぼやけてしまうことがあります。
たとえば、高級ブランドの化粧品と安価な日用品を一緒に陳列すると、ブランドの持つ上質感が損なわれる可能性があります。
顧客側のデメリット
顧客側にもデメリットが発生する恐れがあります。
詳しく見ていきましょう。
意図しない衝動買いにつながる
関連商品が目に入りやすくなるため、お客様が予定していなかった商品まで購入してしまう、いわゆる衝動買いにつながることがあります。
お客様によっては、「不必要な買い物をさせられた」と不満に感じるかもしれません。
探している商品が見つかりにくい
目的の商品が通常とは異なる場所に陳列されている場合、お客様が商品を見つけにくくなる可能性があります。
選べる商品の種類が少なくなる
限られた陳列スペースに複数のカテゴリーの商品を置くため、それぞれのカテゴリーで陳列できる商品の種類が少なくなります。
商品の比較検討をする際は専門コーナーまで足を運ぶ手間がかかる、あるいは探している商品がないと判断して諦めてしまうといった機会損失が発生する可能性も考慮しなければなりません。
専門コーナーに足を運ばなければ複数の商品を比較検討しにくくなります。
クロスマーチャンダイジングを成功に導くポイントと手順
クロスマーチャンダイジングを継続的な売上向上につなげるには、計画的かつ戦略的なアプローチが必要です。
以下に、成功に導くためのポイントと手順をご紹介します。
顧客の購買行動を理解する
まずは、お客様の購買行動を深く理解しましょう。
「Aという商品を買うお客様は、Bという商品も一緒に買う傾向にある」といった関連性を正確に把握することが重要です。
これを特定するためには、POSデータや顧客の購買履歴の分析が効果的です。
たとえば、「アソシエーション分析」と呼ばれるデータマイニング手法を用いると、膨大な購買データの中から、一緒に購入される確率が高い商品の組み合わせを効率的に見つけ出すことができます。
メイン商品を選定する
次に、クロスマーチャンダイジングの中心となるメイン商品を選定します。
メイン商品は、お客様の購買意欲を最も強く引き出す商品を選ぶのがポイントです。
たとえば、季節の変わり目に売上が伸びる主力商品や、CMで大々的に宣伝されている話題の商品などをメインに据えることで、来店客の目を引きやすくなります。
関連商品を選定する
メイン商品が決まったら、次に一緒に陳列する関連商品を選定しましょう。
関連商品は、メイン商品を補完する商品や、メイン商品と一緒に使われることが多い商品を選びます。
たとえば、インフルエンザの流行期に「解熱剤」をメイン商品とするなら、「のど飴」「栄養ドリンク」「マスク」などが関連商品にあたります。
消費者の「あったらいいな」を先回りして提供することで、買い忘れを防ぎ、顧客満足度を高めることができます。
商品を陳列してPDCAサイクルを回す
計画に基づき商品を陳列したら、それで終わりではありません。
実行した後は効果測定を行い、改善につなげることが大切です。
● P(Plan/計画)…購買データに基づいて、メイン商品と関連商品の組み合わせを決める。
● D(Do/実行)…決定した組み合わせで商品を陳列する。
● C(Check/評価)…実施前後の売上データを比較し、客単価や販売個数がどう変化したかを評価する。
● A(Act/改善)…効果が不十分だった場合は、陳列場所や商品の組み合わせを見直し、次の施策に活かす。
このPDCAサイクルを繰り返すことで、より精度の高いクロスマーチャンダイジングを実現できます。
季節やイベントに合わせたテーマを設定する
お客様に新鮮な印象を与え、購買意欲を刺激するには、季節やイベントに合わせたテーマを設定するのが効果的です。
たとえば、夏であれば「紫外線対策コーナー」として、日焼け止め、サンオイル、美白ケア商品などを組み合わせるといった方法が考えられます。
また、季節感やイベント感のある売場は、シーズンファーストバイを逃さないよう早期に展開することで、お客様の購買意欲を自然に高めることが重要です。
売れる売場を効率的に作るならエイジスへご相談ください
クロスマーチャンダイジングによって売れる売場を作るには、シーズンごとに素早く陳列を変更する必要があり、従業員に負担がかかります。残業代など人件費コストも上がりがちです。
そこで、売場づくりを外注するのがおすすめです。
エイジスでは、売れる売場をサポートするさまざまなサービスを提供しております。
集中補充(商品補充・品出し)
店舗スタッフに代わって商品の補充や品出しを行います。
開店前やピークタイムに作業を完了させることで、売場の状態を最適に保ちます。
これにより、店舗スタッフは接客や販売といったコア業務に集中でき、売上アップにつなげることが可能です。
エイジスの「集中補充(商品補充・品出し)」サービスについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
https://service.ajis.jp/service/merchandising/display-replenishment.html
季節の棚替え・カテゴリーリセット
当社の専門チームが、店舗スタッフに代わって棚替えを迅速に実行します。
営業中に作業が可能なため、販売機会を失う心配もありません。52週MD計画に基づいた棚替えも、短期集中で正確に完了させます。
エイジスの「季節の棚替え・カテゴリーリセット」サービスについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
https://service.ajis.jp/service/merchandising/display.html
新店準備・改装リモデル・閉店作業
新店オープンや改装、閉店に関わるあらゆる業務をエイジスグループが一括して承ります。
事前の打ち合わせから、什器の設置、商品陳列に至るまで、全てを専門チームが代行します。営業中や深夜の作業も可能なため、店舗を休業する必要がありません。
これにより、販売機会を失うことなく、顧客の離反を防ぎます。
エイジスの「新店準備・改装リモデル・閉店作業」サービスについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
https://service.ajis.jp/service/merchandising/display-remodelling.html
まとめ
クロスマーチャンダイジングは、お客様の購買行動を深く理解し、関連商品を戦略的に配置することで、客単価と売上を向上させる強力なマーケティング手法です。
適切な商品の組み合わせと効果的な陳列、そしてPDCAサイクルを回すことで、売上アップだけでなく、お客様の満足度向上にもつながります。
しかし、その導入と運用には、陳列や在庫管理の複雑化といった課題も伴います。
エイジスグループでは、お客様の課題解決をサポートし、店舗運営の効率化と売上向上に貢献するサービスを提供しています。
お客様の購買意欲を掻き立てる魅力的な売場を、ぜひエイジスと一緒に作りませんか?



