欠品率とは?欠品率を下げるための方法やおすすめのサービスを紹介

欠品率とは、販売機会に対して商品が在庫切れとなっている割合を示す指標です。
小売業では、「欠品率」の管理が店舗運営の安定性と顧客満足度に直結します。
人気商品の欠品が続けば、売上機会の損失だけでなく、来店客の信頼低下にもつながりかねません。
近年では、原材料費の高騰や人手不足、物流の混乱などにより、欠品リスクが高まる傾向にあります。
そこで、この記事では、欠品率とは何か、その算出方法や基準値を整理した上で、欠品率を下げるための改善策をご紹介いたします。
【関連記事】
欠品が発生してしまう理由とは?リスクや対処方法について解説
商品の補充や品出し、棚替え、改装など、様々な頻度で発生する店舗の”売場づくり”をすべてサポートします。 本資料では、サービスの概要や実績などをまとめて紹介しております。ぜひご覧ください。エイジスのマーチャンダイジングサービス
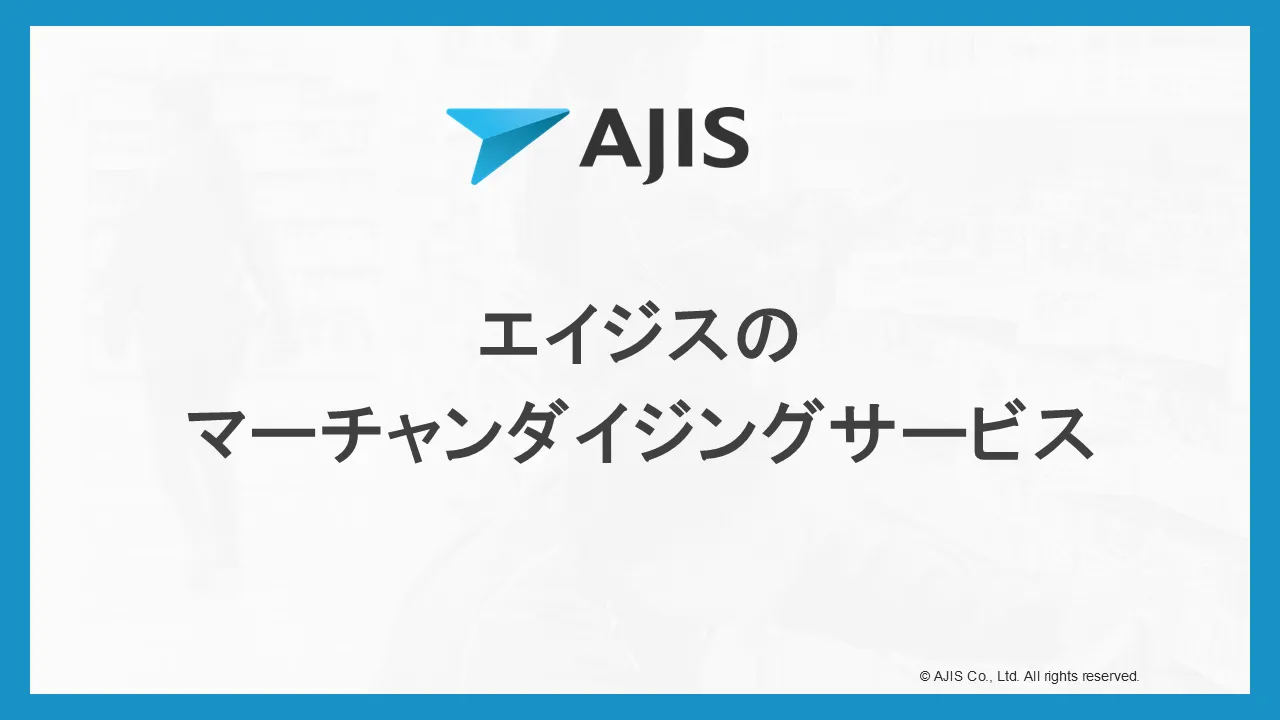
欠品率とは?
欠品率とは、販売機会に対して商品が在庫切れとなっている割合を示す指標です。
一般的に次のような計算式で求められます。
欠品率(%)=欠品数÷発注数×100
欠品率が高いということは、顧客が欲しい商品を購入できない機会が多いことを意味します。
結果として、販売機会の損失や顧客満足度の低下、さらには他店舗への顧客流出を招く恐れがあります。
特にスーパーマーケットでは、食品・日用品といった「日常必需品」が多いため、欠品はブランド信頼性の低下につながりやすくなります。
許容欠品率とは
許容欠品率とは、業務上許容できる欠品の限度を指します。
許容欠品率は、ビジネスモデルや供給チェーンの特性などによって異なります。
欠品率を過度に下げようとすると、過剰在庫のリスクが高まり、保管コストや廃棄ロスの増加につながるため、「欠品率と在庫回転率のバランス」が重要です。
適正在庫を保ちながら、最小限の欠品で運営できる仕組みを整えることが理想です。
欠品率を下げるための方法
欠品率を下げるためには、主に次の5つの方法があります。
倉庫内の整理整頓
倉庫やバックヤードが乱雑だと、商品を探す時間が増えるだけでなく、誤出荷や在庫の見落としが発生しやすくなります。
5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)活動を徹底し、定位置管理を行うことで、欠品の見逃しを防ぐことが可能です。
また、在庫管理システムや棚番管理システムを導入すると、ピッキング精度の向上や棚卸時間の短縮にも効果があります。
入出庫管理の徹底
入庫と出庫のタイミングが曖昧だと、在庫データと実際の在庫数にズレが生じます。
特にドラッグストアやスーパー、ホームセンターなどでは、複数の拠点や物流センターを経由するため、リアルタイムでの在庫更新が欠かせません。
近年では、クラウド型の在庫管理システムを利用することで、各拠点の入出庫データを一元管理し、店舗間の在庫差異を即時に把握できる仕組みが普及しています。
システム導入は初期投資が必要ですが、人的ミスの削減と在庫精度の向上という点で大きな費用対効果が期待できます。
定期的な棚卸の実施
棚卸は「在庫の実数とシステム上の数値を照合する」ために重要な作業です。
定期的な棚卸を行うことで、欠品の早期発見や在庫差異の是正につながります。
とはいえ、手作業による棚卸は時間と人件費がかかるため、外部の棚卸専門サービスを活用する企業が増えています。
たとえば、エイジスグループでも棚卸サービスを提供していますので、ご検討ください。
適正在庫の把握
「欠品が怖いから多めに仕入れる」という判断は、一見、安全策のように見えても、実際には在庫の滞留や廃棄コストを引き起こします。
在庫情報を可視化し、定量的に管理することが、欠品率の継続的な改善につながります。
たとえば、AIを活用した需要予測システムを導入することで、販売データ・季節要因・天候・キャンペーン情報などをもとに、より精度の高い発注判断が可能になります。
発注リードタイムの把握と短縮
発注から納品までのリードタイムが長いと、急な需要増に対応できず、欠品が発生します。
仕入れ先や物流業者と協議し、リードタイムを短縮または柔軟化することが重要です。
また、安全在庫の設定を見直すことで、欠品リスクを抑えることもできます。
発注業務の自動化ツールを導入すれば、需要変動に合わせて自動的に補充発注を行い、発注漏れを防止することが可能です。
欠品率の改善に役立つおすすめのサービス
欠品率の改善には、人力での努力だけでなく、テクノロジーと、さらに外部パートナーの活用が欠かせません。
たとえば、エイジスグループでは、売場の欠品・売価チェックサービスを提供しております。
これは、棚卸や集中補充時に欠品商品のデータをピックアップし、レポートするサービスです。
欠品による機会損失を削減するとともに、集中補充サービスと合わせることで、適正在庫数や適正陳列数の見直しにつなげることができます。
エイジスグループの売場の欠品・売価チェックサービスについて詳しくは、下記のページをご覧ください。
https://service.ajis.jp/service/merchandising/itemchecking-scanchecking.html
まとめ
欠品率とは、販売機会に対して商品が在庫切れとなっている割合を示す指標です。
欠品率を見れば、店舗運営全体の信頼性と効率性を測ることができます。
AIやデジタルツールを活用して、在庫の可視化・需要予測・棚卸の自動化を進めることで、欠品率の低減と顧客満足度の両立が可能になります。
さらに、外部サービスを活用することで、現場の生産性向上と経営効率化をも実現できるでしょう。
店舗運営の安定と顧客信頼を守るためにも、いま一度「欠品率管理」の体制を見直してみてはいかがでしょうか。



